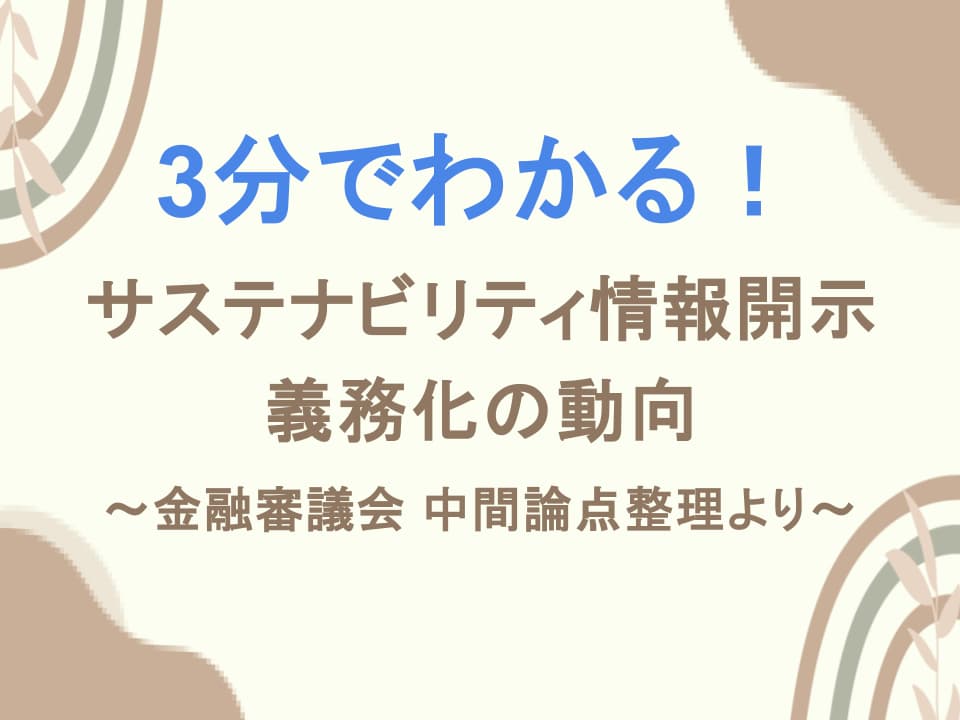待ったなしのサステナ情報開示義務化、貴社は準備できていますか?
企業の経営者、人事、経営企画、そしてIRをご担当される皆様にとって、無視できない大きな変化の足音が聞こえてきています。それは、「サステナビリティ情報開示の義務化」です。
2025年7月17日、金融審議会から公表された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ:中間論点整理」により、これまで任意開示が中心であったサステナビリティ情報が、有報における義務的な開示へと移行する具体的なロードマップが示されました。
これは、単なる報告業務の追加ではありません。投資家が企業を評価する尺度が根底から変わり、企業価値創造のあり方そのものが問い直される、時代の転換点ともいえる動きです。
本コラムでは、この新たな制度のポイントを分かりやすく解説するとともに、これを単なる「守りの対応」で終わらせず、いかにして「攻めの企業価値向上」に繋げていくか、特に「人的資本経営」の観点から、企業が今から取り組むべきポイントを紐解いていきます。
*以下の記事では、今回の中間論点整理のポイントを3分でご理解いただけるよう、なるべく簡単な表現で整理しています。まずは全体像を素早く掴みたい方におすすめです。
なぜ今、サステナビリティ情報開示が義務化されるのか?
今回の決定の背景には、グローバルな潮流があります。ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が国際的な開示基準を策定し 、EUではCSRD(企業サステナビリティ報告指令)によって既に厳格な開示が始まっています。こうした中で、日本企業の情報が国際的に比較可能で、信頼できるものでなければ、グローバルな投資マネーから評価されず、結果として日本市場全体の魅力が低下しかねません。
今回の制度化は、日本企業のサステナビリティへの取り組みを世界標準の「共通言語」で語れるようにし、国内外の投資家との建設的な対話を促進することで、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現することを目的としています。
もはや、財務情報だけで企業価値が測られる時代は終わりつつあります。非財務情報、とりわけサステナビリティに関する情報が、企業の将来性やリスク耐性を判断する上で不可欠な要素となったのです。
今回示された「中間論点整理」の全体像
それでは、具体的にどのような内容が示されたのでしょうか。まずは、公表された「中間論点整理」の概要から見ていきましょう。
中間論点整理の概要
2025年7月17日に金融審議会の「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」が公表した「中間論点整理」は、日本企業におけるサステナビリティ情報の開示と第三者保証の義務化に向けた具体的な道筋を示したものです 。
国際的な潮流を踏まえ、日本市場の信頼性と国際的な比較可能性を高めるため、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が策定した「SSBJ基準」を有価証券報告書での開示基準として採用することが提言されています。
義務化は、プライム上場企業を対象に、株式時価総額に応じて2027年3月期から段階的に開始される予定です。開示された情報には、信頼性を担保するため、SSBJ基準適用の翌期から第三者による「限定的保証」を受けることが義務付けられます。
当初の保証範囲は、Scope1・2のGHG(温室効果ガス)排出量、ガバナンス、リスク管理に限定される方針です。一方で、保証の担い手を監査法人に限定するかどうかや、有価証券報告書の提出期限延長など、結論が出ていない論点も残されており、本年中を目途に引き続き検討が進められます。
論点整理表
重要なのは、各論点がどの程度固まっているのか、その決定状況を把握することです。以下に、今回の発表内容を「決定(◎)」「ほぼ決定(〇)」「検討中(△)」の3つのステータスに分けて整理しました。
| 分類 | 論点 | 概要 |
|---|---|---|
| ◎ | SSBJ基準の採用 | 有価証券報告書において、国際基準と整合性のとれたSSBJ基準に準拠した開示を義務付ける方針が固まりました。 |
| ◎ | 保証水準 | 第三者保証の水準は、企業の負担を考慮し「限定的保証」から開始することが決定されました。将来的な合理的保証への移行は見送られる方針です。 |
| ◎ | 経過措置(二段階開示) | 制度開始初期の負担軽減のため、適用開始から2年間は、有価証券報告書提出後に訂正報告書の形で詳細なサステナビリティ情報を開示する「二段階開示」が認められます。 |
| 〇 | 適用対象企業とロードマップ | プライム市場上場企業を対象に、株式時価総額に応じて段階的に義務化されます。 ・3兆円以上:2027年3月期からSSBJ基準適用、2028年3月期から保証義務化 ・1兆円以上:2028年3月期からSSBJ基準適用、2029年3月期から保証義務化 |
| 〇 | 第三者保証の当初の範囲 | 制度開始から2年間は、保証の対象範囲を「Scope1・2のGHG排出量」「ガバナンス」「リスク管理」に関する情報に限定する方針です。 |
| 〇 | セーフハーバーの整備(初期対応) | 不確実性の高いScope3 GHG排出量などについて、企業が積極的な開示をためらわないよう、まずは開示ガイドラインの改正により、一定の要件下で虚偽記載等の責任を問われにくくする措置(セーフハーバー)が講じられます。 |
| △ | 適用対象企業の拡大 | 株式時価総額5,000億円以上の企業の適用開始時期(2029年3月期が基本線)は本年中を目途に、5,000億円未満の企業への今後の展開については、数年後に結論を出すべく、引き続き検討されます。 |
| △ | 第三者保証の担い手 | 保証業務を監査法人のみに限定するのか、監査法人以外の専門機関にも門戸を開くのか、結論が出ておらず、本年中を目途に引き続き検討されます。 |
| △ | 有価証券報告書の提出期限 | サステナビリティ情報の開示・保証作業の負担増を考慮し、有価証券報告書の提出期限(現行:事業年度経過後3ヶ月以内)を延長するかどうか、投資家の懸念も踏まえ、本年中を目途に結論を出すべく検討中です。 |
| △ | セーフハーバーの拡充 | 法改正も視野に入れた、より広範で実効性のあるセーフハーバー制度のあり方について、継続的に議論される予定です。 |
中間論点整理の核心:いつから、誰が、何をすべきか
上記の全体像を踏まえ、特に企業の実務に直結するロードマップについて、要点を改めて整理します。
対象企業とスケジュール:段階的な義務化がスタート
開示義務の対象となるのは、まずはプライム上場企業です 。ただし、全社一斉ではなく、企業規模(株式時価総額)に応じて段階的に適用が開始されます。
- 株式時価総額3兆円以上の企業:2027年3月期から適用開始
- 株式時価総額1兆円以上の企業:2028年3月期から適用開始
まずは、自社がいつから対象となるのかを正確に把握することが第一歩となります。
開示内容:SSBJ基準への準拠と第三者保証
開示のルールブックとなるのが、日本のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)が策定した「SSBJ基準」です。これは国際基準(ISSB基準)と整合性が確保されており、気候関連情報(SSBJ気候基準)などが含まれます。
そして、今回の制度化におけるもう一つの大きな柱が「第三者保証」の義務化です 。開示された情報が信頼に足るものであることを外部の専門機関がチェックし、お墨付きを与えることが求められます。
- 保証の開始時期:SSBJ基準適用の翌期から
- 保証のレベル:「限定的保証」(財務諸表監査よりは緩やかな水準)からスタート
- 当初の保証範囲:Scope1・2のGHG排出量、ガバナンス、リスク管理に限定
これは、開示情報の「信頼性」を担保するための極めて重要な仕組みであり、企業はデータ収集・管理プロセスの高度化を迫られることになります。
人的資本経営の視点:制度対応を企業価値向上に繋げる3つのポイント
この大きな変革を、単なるコスト増や管理業務の煩雑化と捉えてしまうのは非常にもったいないことです。むしろ、これは自社の経営のあり方を見つめ直し、人的資本経営を深化させる絶好の機会と捉えるべきだと考えられます。
「ガバナンス・リスク管理」:経営層を巻き込んだ推進体制の構築
今回、当初の保証範囲に「ガバナンス」と「リスク管理」が含まれたことは象徴的です。これは、サステナビリティを単なる現場マターではなく、取締役会が監督し、経営戦略と統合された全社的な課題として管理する体制が求められていることを意味します。
<取り組むべきこと>
- 経営層のコミットメント
サステナビリティを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、担当役員を明確にする。 - 部門横断チームの組成
経営企画、IR、人事、サステナビリティ推進、法務など、関連部署が連携する体制を構築する。 - サステナビリティリテラシーの向上
経営層や管理職を対象に、気候変動や人権といったサステナビリティ課題が事業に与えるリスクと機会についての研修を実施する。
これは、まさに人的資本経営における「経営戦略と人材戦略の連動」の根幹をなす部分です。
「戦略・指標」:ストーリーで語る、自社ならではの価値創造
開示で求められるのは、単なるデータの羅列ではありません。自社にとっての重要課題(マテリアリティ)を特定し、それに対する戦略、指標、目標をセットで開示し、進捗を管理する、一連のストーリーが求められます 。
例えば、「気候変動への対応」というテーマ一つをとっても、
- 自社の事業にとってのリスクと機会は何か?
- そのために、どのような技術革新や事業ポートフォリオの見直しを行うのか?
- それを実現するために、どのようなスキルを持つ人材が必要で、どのように育成・獲得していくのか?(リスキリング、グリーン人材の採用など)
このように、サステナビリティ戦略と人的資本戦略は不可分です。開示を通じて、自社がどのように社会課題の解決と経済的価値の創出を両立させ、持続的に成長していくのか、その独自のストーリーを投資家に語ることが重要になります。
「データ収集と信頼性」:データドリブン人事への変革
第三者保証が義務化されることで、開示する情報の正確性、網羅性、継続性が厳しく問われます。特に、GHG排出量のような定量データは、算出根拠を含めた管理プロセスの構築が不可欠です。
これは、人事領域においても同様のことが言えます。例えば、2023年3月期から開示が義務化された女性管理職比率や男女間賃金差異といった人的資本に関する指標は、今回の保証義務の直接の対象ではありません。しかし、今後、非財務情報全般に対する信頼性向上が求められる潮流の中で、これらの指標についても、そのデータ管理のあり方を見直すことは、企業価値向上の観点から一つの論点となり得るでしょう。
<取り組むべきこと>
- データ収集プロセスの標準化
誰が、いつ、どのシステムのどのデータを使って集計するのか、プロセスを明確化・文書化する。 - データの一元管理
人事システムやタレントマネジメントシステムを活用し、分散しているデータを統合・管理する基盤を整備する。 - 内部統制の構築
データの正確性を担保するためのチェック体制を構築する。
この取り組みは、サステナビリティ開示のためだけにとどまりません。信頼性の高いデータを基盤とすることで、より客観的で効果的な人事施策の立案・実行、すなわち「データドリブンな人的資本経営」への変革を加速させることに繋がります。
未来への羅針盤として、今こそ行動を
サステナビリティ情報開示の義務化は、もはや避けては通れない現実です。しかし、これを脅威ではなく機会と捉え、自社の経営と人的資本のあり方をアップデートしていくことで、企業は新たな成長軌道を描くことができると考えられます。
まずは、中間論点整理の内容を正しく理解し、自社の現在地を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。そして、経営層を巻き込み、部門の壁を越えて、全社一丸となってこの変革に臨むことが、未来の企業価値を左右する鍵となるでしょう。
株式会社コトラでは、人的資本経営に関する深い知見と豊富な実績で、貴社の課題解決をサポートします。より具体的なご相談は、お気軽にお問い合わせください。