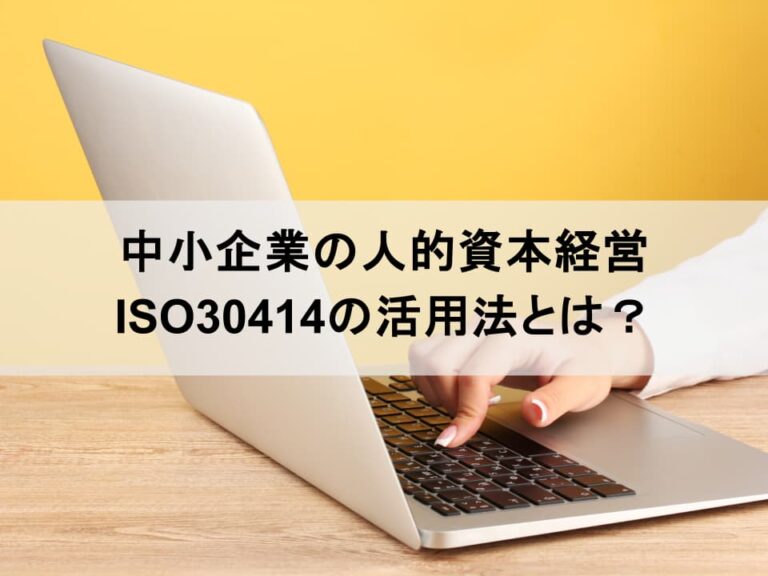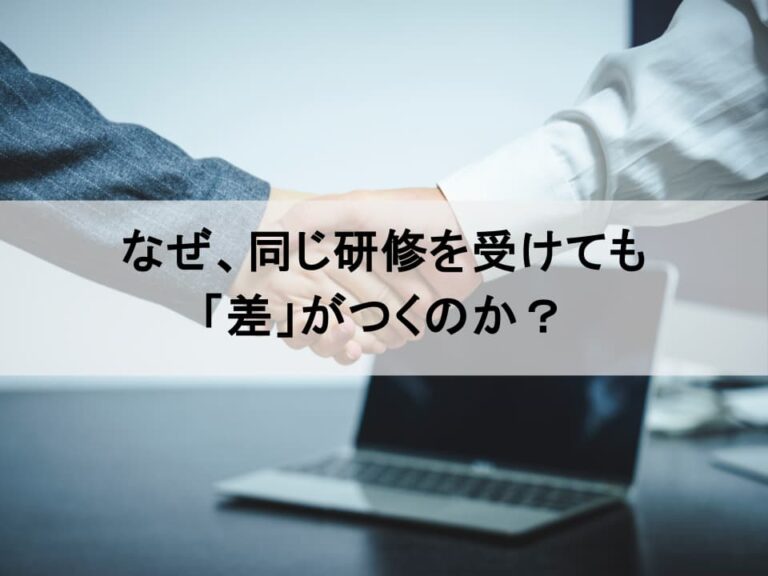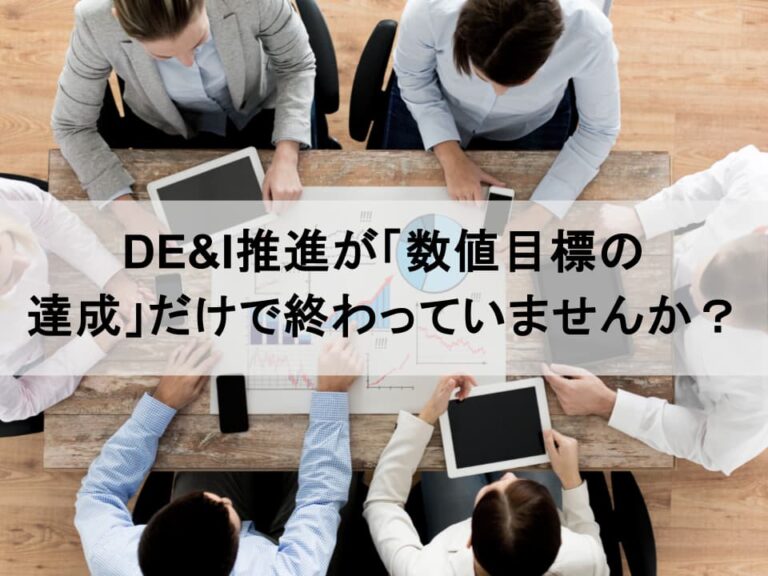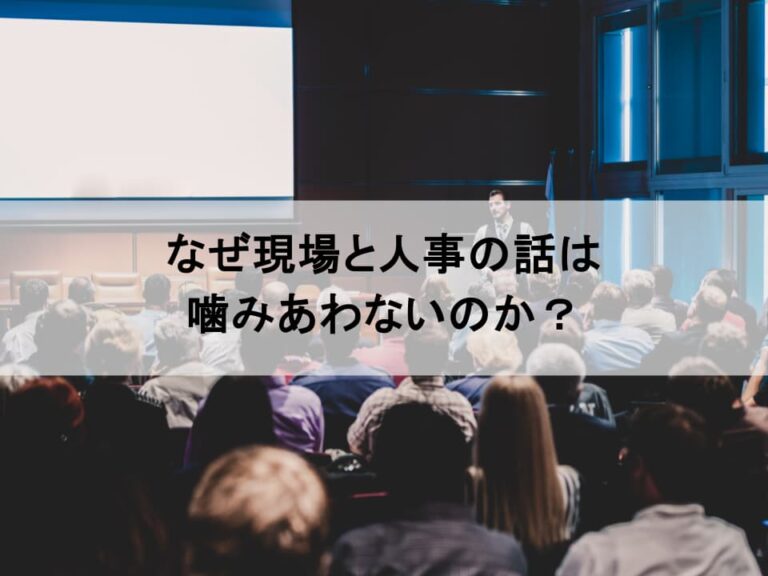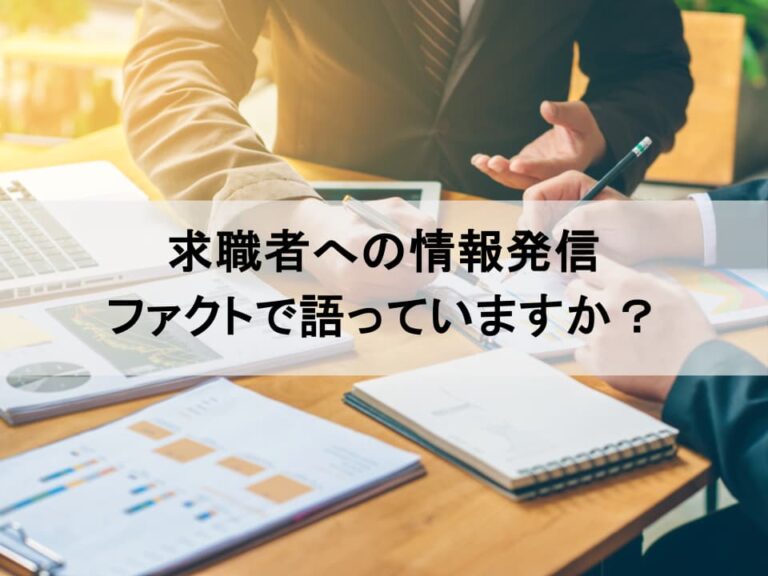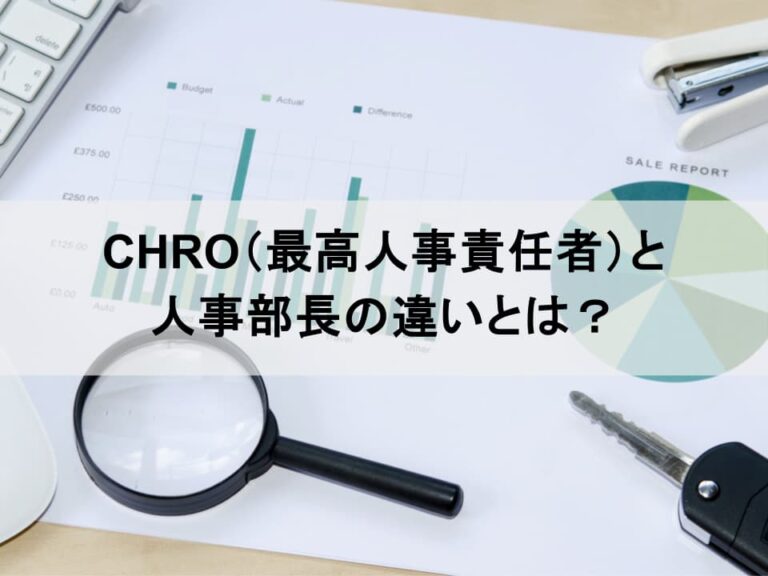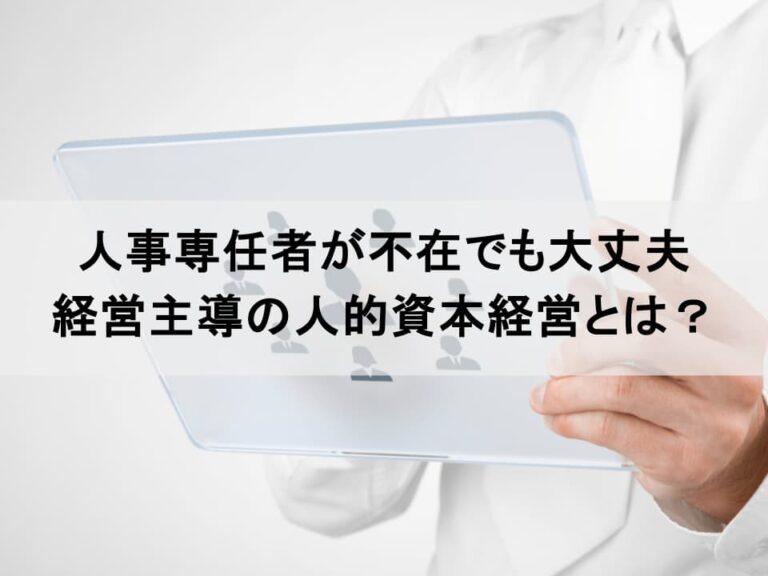-
 人的資本経営・開示
人的資本経営・開示 中小企業こそ「人的資本経営」で勝つ|ISO 30414認証という差別化戦略
中小企業が「選ばれる」ために:攻めの人的資本経営 「知名度や資金力で勝る大手に、人材獲得でどう対抗す […] -
 人的資本経営・開示
人的資本経営・開示 「全社員をハイパフォーマーに育てる」ことは可能か?|教育コストの最適配分
なぜ、同じ研修を受けても「差」がつくのか 「トップ営業であるAさんのノウハウを、全社員に展開したい」 […] -
 人的資本経営・開示
人的資本経営・開示 ダイバーシティKPI|「数合わせ」を脱却し競争力へ転換する
ダイバーシティ推進のプレッシャーと、現場の疲弊 「女性管理職比率を30%にするという目標が降りてきた […] -
 人的資本経営・開示
人的資本経営・開示 「現場が動かない」と嘆く前に|戦略人事が持つべき共通言語
「人事は現場を分かっていない」という壁 新たな人事制度や評価基準を導入しようとしたとき、現場の管理職 […] -
 人的資本経営・開示
人的資本経営・開示 応募数減少の打開策:美辞麗句を捨て「ファクト」を語れ
求職者への情報発信、ファクトで語っていますか? 「求人票には良いことばかり書いてあるが、実態はどうな […] -
 人的資本経営・開示
人的資本経営・開示 採用難と離職を防ぐ「従業員価値提案(EVP)」の設計論
人材獲得競争の勝敗を分ける「選ばれる理由」 「求人を出しても応募が来ない」「内定辞退が増えている」「 […] -
 人的資本経営・開示
人的資本経営・開示 人的資本経営の要「CHRO」:人事部長との違いと経営を動かす3つの役割
なぜ今、日本企業に「CHRO」が必要なのか グローバルで加速する人的資本経営の流れを受け、日本企業で […] -
 人的資本経営・開示
人的資本経営・開示 人事部不在の中小企業こそチャンス|社長主導で始める人的資本経営
人事部がなくても人的資本経営は可能か 「人的資本経営」という言葉を聞くと、専門知識を持った人事部員が […] -
 人的資本経営・開示
人的資本経営・開示 「上司が理由」の離職を止める:プレイングマネージャーの限界と組織的支援
なぜ、あの部署ばかり人が辞めるのか? 「特定のマネージャーの下で、退職が相次いでいる」 このような事 […]